血便は出血性大腸炎の典型的な症状ですが、痔や大腸ポリープ、大腸がん、腸重積※4などさまざまな原因でも起こることがあるため、それらの病気と正確に鑑別することが重要です。 いずれにしても血便が続くような場合には治療が必要になることが多いため、できるだけ早く医療機関を受診することをおすすめします。
※4 腸重積:腸管の一部が後ろの腸管に引き込まれ重なってしまう状態。
大腸の粘膜に起きた炎症により、突発的に血便 (血性下痢:血の混じった下痢)や腹痛などを引き起こす病気を「出血性大腸炎」と言います。
出血性大腸炎には、治療のために服用した薬剤の副作用によって起こるものと、細菌に感染することによって起こるものがあり、病気の種類や炎症の状態によって重症度が異なります。
出血性大腸炎を発症した場合、下痢や血便などが続くと身体から多くの水分が失われてしまうため、十分な水分の摂取が重要であり、症状や重症度に合わせた適切な治療が必要になります。
出血性大腸炎では、大腸内腔の表面を覆っている粘膜が炎症を起こして出血することにより、血便の症状が現れます。
出血性大腸炎には、抗生物質の副作用によって起こる「薬剤性大腸炎(抗生物質起因出血性大腸炎)」と、病気を引き起こす細菌(病原大腸菌)に感染して発症する「腸管出血性大腸炎」の大きく分けて2つの種類があります。
血便の量や回数は、病気の種類や重症度によっても若干異なりますが、最初は水のような下痢から始まって徐々に血が混じるようになり、次第に真っ赤な血液そのものという状態に変わっていくのが典型的な症例です。また、血便以外の症状として強い腹痛を伴うことが多いですが、熱が出ることは少なく、発熱した場合でも38℃を超えるようなことはあまりありません。
無症候(症状がない)やごく軽症で済む場合もありますが、下痢や血便が続き身体から多量の水分が失われてしまうと、脱水症を引き起こすリスクが高まるため、状態によっては点滴による水分補給などの適切な処置が必要になります。
また、細菌性の出血性大腸炎の場合、小さなお子さんや高齢者の方は重症化して深刻な合併症を引き起こし、命に関わることもあるため十分な注意が必要です。
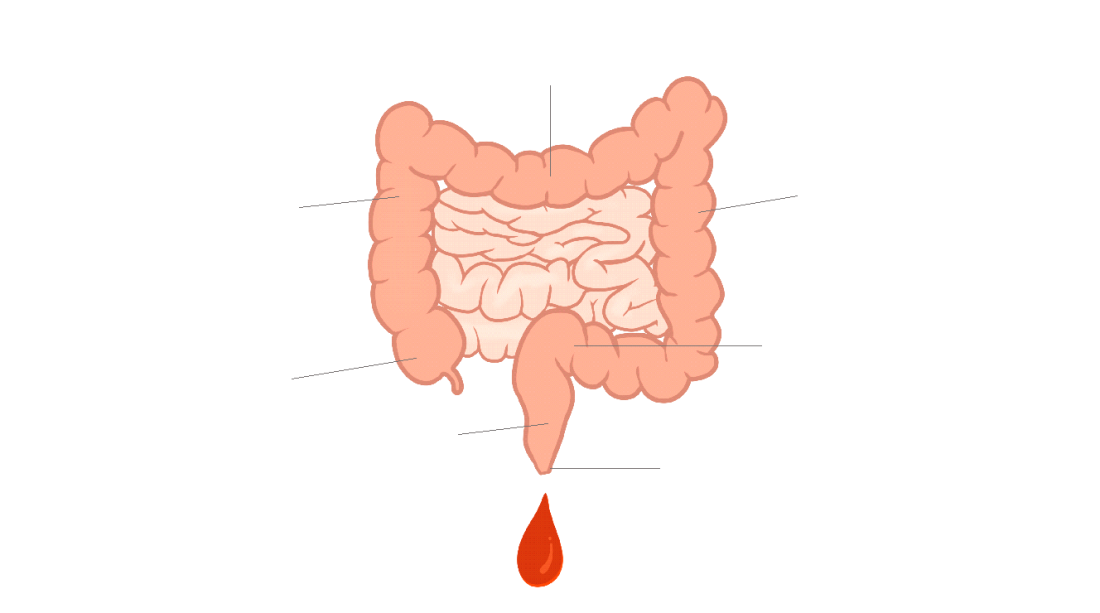
抗菌薬を服用した数日後に突然発症する急性の出血性大腸炎で、「抗生物質起因性出血性大腸炎」とも呼ばれています。
特に「ペニシリン系」と呼ばれる抗菌薬による発症が多いですが、「セフェム系」やその他の抗菌薬でも起こる場合もあります。
上行結腸から横行結腸、下行結腸の粘膜の表面に発赤(赤み)やむくみ(浮腫)、ただれ(びらん)、出血などが起こることが多く、盲腸や直腸に病変ができることはほとんどありません。
10~20代の若者など、若い年齢層に多く見られます。特別な基礎疾患のない人でも発症することがあります。
抗生物質の服用後2~3日程度で腹痛や水のような下痢が起こり、徐々に血便に変わります。
比較的軽症の場合が多く、患者さんによっては腹痛がない場合もあります。
発熱を伴うこともありますが高熱が出ることはありません。
薬剤に対する過剰な反応(アレルギー)や菌交代現象*1によるものという説がありますが、はっきりとした解明はされていません。
*1 菌交代現象:治療目的で投与した抗菌剤の影響を受けて、腸内細菌の中のある種の細菌が異常に増殖する現象のこと。
病気を引き起こす原因となる大腸菌(病原大腸菌)が作り出す毒素によって引き起こされる急性の出血性大腸炎で、「EHEC感染症」とも呼ばれます。
腸管出血性大腸菌は牛や羊などの家畜の大腸に生息している菌で、「O157」による集団発生が良く知られていますが、日本国内では「O26」「O111」などによる発症も報告されています。
感染力が非常に強く、50個程度の少ない菌量でも発症するため注意が必要です。
食中毒による発症が多いことから気温が上がる夏に多く見られますが、冬場に発症するケースもあります。
腸管出血性大腸炎は無症候性や軽症の場合もありますが、重症化すると深刻な合併症を引き起こすのが特徴で、発症者の6~9%程度に「溶血性尿毒症症候群(HUS)*2」や脳症などの合併症が起こることが分かっています。
HUSを発症した方の半数程度は腎臓透析*3が必要になり、抵抗力の弱い小さなお子さんや高齢者の場合は命に関わることもあるため注意が必要です。
*2 溶血性尿毒症症候群:全身に小さな血栓ができて脳や心臓、腎臓などへの血流を妨げてしまう病気。溶血性貧血、血小板減少、腎機能障害が起きるのが特徴です。
*3 腎臓透析:腎臓の働きが悪くなった場合に、体内の老廃物や過剰な水分を取り除くために行う処置。
全年齢で発症することがあります。小さなお子さんや高齢者の方はHUSや脳症などの合併症を起こすリスクが高くなります。
3~5日程度の潜伏期間を経て、水のような下痢が1~3日続いた後に血便が起こります。
強い腹痛や嘔吐を伴うことが多いですが、発熱はないか、発熱しても37℃台の軽症です。(稀に39℃を超えるような場合もあります。)
病原大腸菌に汚染された生肉や水、野菜などを直接または間接的に摂取することで経口感染します。湖などの水を介した感染、動物との接触によって感染する場合もあります。
患者の排泄物などを介し、ヒトからヒトへ二次感染することもあり、おむつをしている赤ちゃんから感染するケースが多くなっています。
出血性大腸炎の診断は、発症状況を確認するための問診が非常に重要になります。
自覚症状や発症時期、摂取した飲食物、服薬の有無、海外渡航歴など、患者さんのお身体の状態や行動内容などを詳しくお伺いし、出血性大腸炎が疑われる場合には必要に応じて以下のような検査を行います。
便を採取し、培養することで病原性のある細菌の有無や毒素がないかを調べます。
採血を行い、白血球やCRP、血沈値などから炎症反応や貧血の有無などを調べます。
肛門から内視鏡を挿入し、大腸内の粘膜の状態(赤みや腫れ、出血など)を確認します。
出血が確認される場合には、出血の量や部位、大きさなどを考慮し、内視鏡を使用した止血(内視鏡的止血術)を行う場合もあります。
当院の大腸カメラ検査は「NBI(狭帯域光観察)」と呼ばれる内視鏡診断システムを導入しています。
「NBI=Narrow Band Imaging」は、青や緑などの短い波長の光を使用することで、腸などの消化器の粘膜の表面にある血管を鮮やかに浮かび上がらせる性質があり、より精密な検査が可能になります。
大腸カメラ検査の詳細については「大腸カメラ検査ページ」にて説明しています。
※ただし、検査結果が出るのに時間がかかる場合があるため、患者さんの状態から推測し、先行して治療を開始するケースもあります。
出血性大腸炎の治療では「絶食」「安静」「十分な水分補給」といった保存療法が基本で、必要に応じて整腸剤などによる対症療法を行います。
軽症の場合、脱水を起こさないように水分をしっかり摂取し、身体の安静を保ち免疫力を高めることで徐々に症状が消失し、1週間程度で自然治癒します。
ただし、頻繁に下痢や血便が見られ、身体から多量の水分が失われてしまっている場合には、点滴で静脈の血管から水分や電解質を補う「輸液(ゆえき)」が必要になります。
原因となった薬剤の使用を中止し、整腸剤などの対症療法を行うことで、徐々に症状が治まります。粘膜に瘢痕(はんこん:傷跡)などが残ることもなく、1週間以内に治癒するケースが多いです。
やむを得ず抗菌薬の服用を続ける場合には他のタイプの抗菌薬への変更を検討します。
軽症の場合、安静と水分補給を行うと菌の産生した毒素が徐々に体外に排出されて1週間程度で症状が消失します。
ただし、小さな子供や高齢者、その他免疫力の低下している方は重症化して合併症を起こす可能性が高く、脳症やHUSを発症した場合は入院治療が必要になります。
なお、下痢止めや痛み止めなどの薬は腸管の運動を抑える働きがあり、毒素が排出されにくくなるため、通常は使用しません。また、抗菌薬の使用についてはHUSの発症を誘発するという見方と発症早期に使用するとHUSの発症率を下げるという両方の見解があるため、慎重に検討します。
急性期には食事を摂るのを一旦中止して、腸の安静を保つことが大切です。
必要な水分は、お茶や水よりも糖分や電解質をバランスよく含んだ経口補水液やスポーツドリンクを摂るようにします。
飲み方は、一度にたくさん摂取するのではなく、常温のものを少量ずつこまめに摂取するようにしましょう。
通常は、数日程度で血便や腹痛などの症状が改善します。症状が落ち着いてきたら状態を見て、お粥や柔らかく煮たうどんなど、消化に優しいものから食事を徐々に再開します。
※経口で水分が摂れなくなった場合や腹痛がなかなか治まらない場合、痛みがさらに増すような場合には速やかに受診することが大切です。
血便は出血性大腸炎の典型的な症状ですが、痔や大腸ポリープ、大腸がん、腸重積※4などさまざまな原因でも起こることがあるため、それらの病気と正確に鑑別することが重要です。 いずれにしても血便が続くような場合には治療が必要になることが多いため、できるだけ早く医療機関を受診することをおすすめします。
※4 腸重積:腸管の一部が後ろの腸管に引き込まれ重なってしまう状態。
腸管出血性大腸菌は食中毒による発症が多いため、以下のような点に気を付け、衛生環境を良くすることが大切です。
腸管出血性大腸炎は学校保健法により「第3種感染症」に定められています。
病状によって学校医またはその他の医師から感染の恐れがないと認められるまでは出席停止となっていますので、担当医の指示に従ってください。
詳しくは日本学校保健会のサイト(外部)をご覧ください。
出血性大腸炎は、薬剤によるものか感染によるものかで重症度も大きく異なりますが、基本的には安静を保ち、脱水予防のための水分補給をしっかり行うことが大切になります。
軽症の場合、どちらも通常1週間程度で完治が可能ですが、患者さんの状態によっては症状が長引いたり、重症化して合併症が起きたりするケースがありますので、血便症状が起きた時には早めに当院にご相談ください。